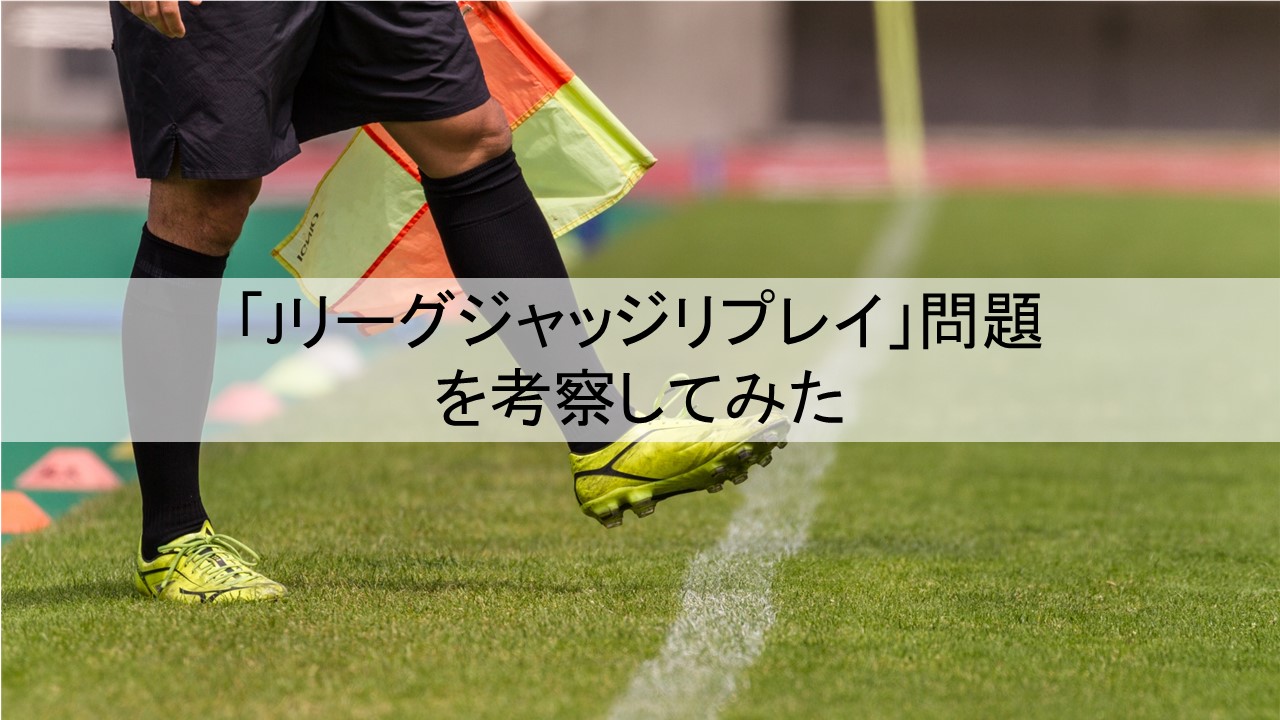先日メディアやSNSで話題となった「Jリーグジャッジリプレイ」問題。
問題の発端は、番組内での原博実(Jリーグ副理事)さんの発言に、ヴィッセル神戸の三浦淳寛(SD:スポーツダイレクター)さんが不快感を示したというもの。
今回は一連の騒動の流れを整理するとともに、発言の意図を考察してみたいと思います。ややデリケートな内容となりますが、お手柔らかに(笑)
「Jリーグジャッジリプレイ」って何?
さて、そもそも「Jリーグジャッジリプレイ」とは何か?という点から解説しておきましょう。
DAZNが配信する人気コンテンツ
ジャッジリプレイは、DAZNが配信しているオリジナルコンテンツです。毎週Jリーグの各試合の中から、視聴者や出演者が疑問に思った審判のジャッジを取り上げ、解説を行うという内容となっています。
番組はJリーグの原博実副理事長と、サッカー番組ではお馴染みの平畠啓史さんがレギュラーとして出演。さらにゲストとして、JFAの審判委員が週替わりで登場し、上川徹さんやレイモンド・オリバーさん、扇谷健司さんといったレフェリー部門のトップ達がジャッジを分かりやすく解説してくれます。
疑問に残った判定を細かく検証し分析してくれる番組とあって、 サポーターからも 人気の高いコンテンツとして知られています。
ちなみにDAZNに加入していなくても、 YouTubeのJリーグ公式アカウントが毎回動画をアップしてくれているので、興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね!
選手・レフェリー・サポーターの3つの目線が取り入れられている
ジャッジリプレイの良い点は、原さんが選手(監督など現場の声)、上川さんらがレフェリー、平畠さんがサポーターと、それぞれの目線で解説を行っている点です。
やはり試合の判定には、どうしても見る人の立場によって主観が反映されてしまいす。だからこそレフェリーの判定が物議をかもすわけですが、この番組ではまず最初に原さんと平畠さんが私見を述べ、上川さんらがレフェリー目線で解説をするという構成となっています。
つまり、主観と客観をあえて混ざて番組を構成しているということ。こうすることで、サポーターにとっても共感を持ちやすく、魅力あるコンテンツができあがっています。
問題のシーンを解説 │三浦さんが不快感を示した訳は?
さて、ここからが今回のテーマの本題。
問題となったのは、こちらの3:47~あたりの場面です。
議論の焦点となった原さんの発言とは?
テーマは4月6日に行われた、J1第6節のヴィッセル神戸vs松本山雅の試合。ウェリントンがコーナーキックに合わせて決めたへディングシュートが、ファールの判定で取り消された場面です。
たしかにこの判定は、ゲームを観戦していた自分も誰がファールなのか?なぜゴールが取り消されたのか?よく分からないシーンでした。
この判定について番組では、上川さんがリプレイを再生しながら丁寧に解説し、「ヴィッセル神戸の大崎がファールのため、ゴールは取り消された」と説明してくれました。
上川さんはこの解説を前に、実際にジャッジを下したレフェリーに電話で確認もとっているとのこと。解説の内容は動画をご覧いただいた方は分かるかと思いますが、個人的には非常にロジカルで納得のいく解説だったと感じています。
さて、これだけならいつものジャッジリプレイだったのですが、問題となるのはこのプレーに対しての原さんのコメント。3:47分あたりに原さんは、大崎のディフェンスに関して「(守り方が)ヘタ。もうちょっとうまくやらないと」と発言しました。
三浦SDが「言葉を選んで欲しい」と不信感を示す
この発言に不信感を示したのが、ヴィッセル神戸の三浦スポーツダイレクターです。三浦さんはメディアからの取材に対して、次のように語りました。
「原さんはすごく良い人だし、個人的にも好きな人」と前置きしつつも「大崎を始め、選手は命がけで戦っている。もうちょっと言葉を選んで欲しい。あの言葉は本人含め、クラブ関係者は良い気分はしないですよね」
デイリースポーツhttps://www.daily.co.jp/soccer/2019/04/11/0012230951.shtml
三浦さんは現在、ヴィッセル神戸の強化部の最高責任者にあたるスポーツダイレクター(SD)を務めています。三浦さんの発言は、ピッチで必死に戦っている選手に対して、Jリーグの副理事を務める立場の人間が発する言葉として、不適切(軽はずみ)だったのではないのか?という意味合いだったと受け止められます。
たしかに、「ヘタ」という言葉やや乱暴過ぎる印象も与えますね。解説や動画配信を見ている方にはお馴染みですが、原さんは比較的ストレートに意見を述べるタイプです。
この正直さが原さんの魅力でもありますが、現場に近い立場にいる三浦さんとしては、一言述べておきたかったということでしょう。
三浦さんの発言の裏には何があったのか?
しかし、選手を守りたい立場とはいえ、わざわざメディアを通じてコメントを発するのは異例と言えます。では、なぜ三浦さんはこのような発言をしたのでしょうか?
曖昧さが目立った松本戦のジャッジ
実はこの日の松本山雅との試合では、このシーン以外にもいくつか疑問の残る判定が続いていました。とくにヴィッセルに対してやや不利となるような判定が多く、試合後には関係者からこんな意見も聞こえてきました。
レフェリーのレベルは低かった試合だけど
— 西大伍 Daigo Nishi (@daigonishi22) April 6, 2019
それ以外のところでもっとやらなきゃね
あとは、文句ではなく意見にするべき
それでも両チームのサポーターの皆さんは素晴らしかった
ありがとう#品位 #意見具申
VARが高いという意見を頂きましたが、今やプロsportではビデオ判定は常識。また、世界では八百長が最大の問題であり、VAR必須です。ワールドカップ、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパの各リークだけでなく、アメリカのMLSでも既に導入されています。ビデオ判定による公平性がリーグの魅力をあげます。
— 三木谷浩史 H. Mikitani (@hmikitani) April 6, 2019
もちろん、負けたチームの関係者がジャッジに対して疑問を呈していても、そのまま意見を鵜呑みにすることはできません。
しかし、90分のゲームを通して見ても、この日のレフェリングは安定感を欠いていた点は事実でしょう。
実際ジャッジリプレイの中でも、松本サポーターから「ジャッジに曖昧さがあった」との意見も届いています。
90分トータルで審判のレフェリングに対して疑問があったのでは?
さて、この事実から推測してみると、三浦さんの発言は「90分間のゲームを通してのレフェリング」に対して向けられたものとも受け取ることができます。
メディアには原さんの発言に対しての不信感を示していますが、やはり曖昧さが目立った松本戦のジャッジへ疑問を感じていたのではないでしょうか?
もちろんこれはあくまでも推測ですが、こうした心理的背景が三浦さんの発言に影響したとも考えられるでしょう。
「ミスジャッジ もサッカーの一部」という危うさ
もう一点言及しておきたいのが、「ミスジャッジもサッカーの一部」という考え方の危うさです。
審判の判定に疑問が残ると、ついつい「ミスジャッジ もサッカーの一部」と無理に納得してしまうことがあります。自分自身も、サポーターという立場でこのように考えた経験が何度かありました。
しかし、これは実際にピッチでプレーしている選手や、現場を預かる関係者たちからすれば看過できない意見でしょう。彼らにとっては三浦さんの発言にあるように、毎試合が「命がけ」の戦いの連続です。
プロスポーツは毎試合が勝負。ワンゲーム。ワンプレーが自身やクラブの未来を左右します。こうした現場のシビアな空気感が、三浦さんの発言に込められているとも言えるでしょう。
自戒も込めて、安易に 「ミスジャッジもサッカーの一部」 と考える危うさを持っておきたいと思います。
サポーターの意見もさまざま
サポーターのあいだでもこの問題に対してさまざまな意見が飛び交っています。
SNSでのサポーターのみなさんの声
これまで審判委員会の意見を知ることができなかったのに、ブリーフィングによって記者次第で知ることができるようになり、次いでジャッジリプレイの誕生で月1でいくつかを知ることができるようになり、現在は週1でいくつかを知ることができる
— 攻劇@一時的退場中 (@18kogekisoccer) April 8, 2019
これで「あれがないとか援護かよ」って文句言うのはなぁ
ジャッジリプレイ見た。上田益也主審を「ファインプレー」と賞賛する内容。
— llnɟʞ00q (@bk_roccaguaita) April 8, 2019
私はこの基準だと日本にマリーシアは育たない(=いつまでも狡猾なプレーに愚弄される)と思った。
またノーゴール判定のウエリントンが「またかよ」という表情をした原因、不安定な判定基準があった経緯も無視されている。
やはりそれぞれの立場や考え方によって、さまざまな捉え方や意見が飛び交っていますね。
原さんは審判にも容赦なくミスジャッジと述べる
さて、個人的に気になったのは、「原さんはJリーグ側の人間だから、審判を擁護しているのでは?」という意見です。
この疑問をお持ちの方には、ぜひこの回以外のジャッジリプレイも見ていただきたいのですが、原さんはジャッジリプレイの中で審判に対してもはっきりと「ミスジャッジ」と意見を述べています。
毎回視聴している自分の主観ではありますが、決して審判を擁護する意図があるとは見受けられません。
ただ、今回の三浦さんも指摘したように、原さんの立場がJリーグの上層部にあるという点は、誤解や批判を受けてしまう可能性は否定できません。とくに原さんのストレートな物言いは、物議をかもす一因ともなってしまうでしょう。この点は、メディアコンテンツを制作する上でバランス感覚を大切にする、という話になってくるのではないでしょうか。
まとめ
今回はサッカーファンや現場でも意見が飛び交った、「Jリーグジャッジリプレイ」問題について考察してみました。
こうしてじっくり問題を考察してみると、立場や意見は違いや発言者のパーソナリティーなど、複合的な要因が重なっているように感じます。
明日配信のジャッジリプレイでは話題となっている松本vs神戸についても長く触れています。
— 桑原学 (@kuwaharamanabu) April 8, 2019
今回で#6となりますが、この番組の意義をこれまで以上に強く感じる回となりました。
ぜひ多くの方に見て頂きたいと思いますので、サッカーファンの皆さん、よろしくお願いします!
番組MCの桑原さんは、今回のジャッジに限定せず、普段のJリーグのジャッジに対してこのようなコメントを残していました。
ジャッジリプレイの配信より
「これが逆の印象になって、日本のレフェリーはレベルが低い、みたいなことを広められてしまうことがすごく残念」
逆の印象とは、実際は審判の好判断だったにも関わらず、主観的な意見だけで事実と反するイメージが広がってしまうということ。たしかにJリーグのレフェリングの精度を向上させることはリーグの発展に欠かせませんが、良いジャッジには拍手を送り、間違ったジャッジはしっかり検証し改善する、というスタンスが望ましいと言えます。
今回は物議をかもしたジャッジリプレイですが、今後もJリーグの発展のためにさまざまなシーンを取り上げてもらいたいですね!
以上フットボールベア―でした!